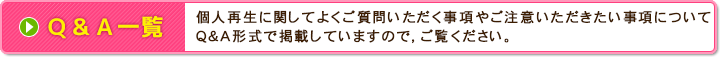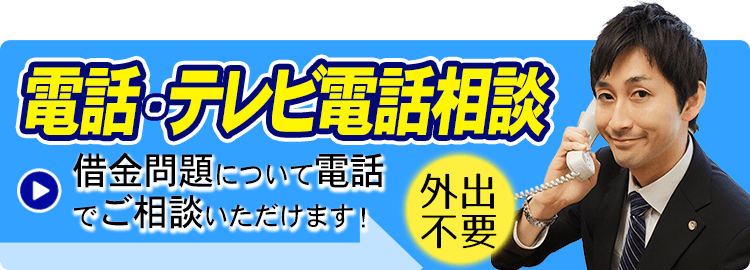お役立ち情報
個人再生に反対する業者(債権者)がいるとどうなるのか
1 反対が多いと債務の減額が認められない可能性がある
個人再生は、借金の元本を大幅に減額することで、債務の負担を大きく軽減できる制度です。
その反面、債権カットの不利益を受ける債権者の中には、個人再生に反対する者も出てくることが予想されます。
反対債権者の数が一定以上に達すると、個人再生による債務の減額が認められないおそれがありますので、状況に応じた対処が必要です。
今回は、個人再生に反対する債権者がいた場合の対処法について解説します。
2 個人再生において、債権者の反対が問題となるケース
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
債権者の同意が必要となるのは、このうち小規模個人再生のみです。
小規模個人再生の場合、債務の減額等の内容を定めた「再生計画案」について、債権者による決議を経る必要があります。
債務者から裁判所に再生計画案が提出されると、裁判所はその再生計画案を決議に付する旨の決定を行います。
再生計画案に反対する債権者は、裁判所の定める期間内に、不同意の旨を回答しなければなりません。
不同意債権者が、以下のいずれかの数を超過した場合、再生計画案は否決されてしまいます。
⑴ 不同意債権者の数が、債権者総数の半数以上の場合
債権者の半数以上が再生計画案に反対している場合、その再生計画案は否決されてしまいます。
特に、債権者総数が少ない場合は注意が必要です。
たとえば債権者が2社しかおらず、その中の1社が再生計画案に反対しているとします。
この場合、「不同意債権者の数が、債権者総数の半数以上」という再生計画案の否決要件を満たしてしまいます。
上記のように、債権者数が少ない状況では、1社、2社程度の反対債権者がいるだけで、再生計画案が否決されることになってしまうのです。
債権者数が少ない分、各債権者の発言力は相対的に大きくなるので、債務者としても難しい調整を迫られることが予想されます。
⑵ 債権額の過半を占める債権者が反対している場合
大口債権者が反対している場合には、再生計画案が否決される可能性が高いです。
たとえば、債権者は10社いるものの、そのうちの1社が総債権額の過半を占めているとします。
この場合、大口債権者である1社が反対すれば、「不同意債権者の有する債権額が、債権総額の2分の1超」という再生計画案の否決要件を満たしてしまうのです。
仮に大口債権者の債権額が、債権総額の2分の1超に達していなかったとしても、それに近い水準であれば、残りの債権者の一部が反対に回った場合、やはり再生計画案は否決されてしまうでしょう。
したがって、個人再生を進めていくに当たっては、大口債権者の意向に十分気を配る必要があります。
また、反対に大口債権者だけが同意していても、他の小口債権者の反対によって、再生計画案が否決されてしまうこともあります。
たとえば、債権者が10社いて、総債権額の過半を占める1社は再生計画案に同意しているものの、残り9社がすべて反対しているようなケースです。
この場合、「不同意債権者の数が、債権者総数の半数以上」という要件を満たし、再生計画案は否決されてしまいます。
否決のボーダーラインを大きく上回る数の債権者が反対している場合には、各債権者を順番に説得していくのは、かなり大変な作業になる可能性が高いです。
3 個人再生に反対する債権者がいる場合の対処法
個人再生に反対する債権者に対しては、弁護士を通じて説得を試みるのが基本になります。
しかし、説得が奏功しないケースも考えられますので、その場合は再生計画案の見直しを行ったり、別の債務整理手続きの利用を検討したりすることも必要になるでしょう。
⑴ 反対債権者を説得する
反対債権者に対しては、「再生計画案に賛成した方が、結果的に債権者にとっても有利になる」と説得することが有効です。
個人再生が頓挫した場合、多くの債務者は自己破産を選択します。
自己破産では、債権者が受け取れる配当はほんの僅かであり、配当が全くないケースも珍しくありません。
これに対して個人再生では、「清算価値保障原則」が存在します。
清算価値保障原則とは、個人再生手続きにおける弁済額を、破産手続きや特別清算手続きにおける債権者への配当よりも多くなるように設定しなければならないという原則です。
つまり、債務者を自己破産に追い込んでしまうよりも、再生計画案に同意して個人再生による弁済を受ける方が、債権者にとっては有利となります。
このことを丁寧に説明すれば、債権者も翻意して、再生計画案に同意してくれる可能性があるでしょう。
⑵ 再生計画案の内容を見直す
債権者が再生計画案に反対しているのは、「弁済額が期待していたよりも少ない」などと感じているからかもしれません。
この場合は、再生計画案を一部変更し、反対債権者の不満を解消してあげることで、再生計画案への同意に転じてくれる可能性があります。
具体的にどのようなポイントに不満を持っているのかをヒアリングし、そのうえで他の債権者との利害調整を行いつつ、決議が得られるような再生計画案の内容に仕上げていくことが重要になります。
⑶ 給与所得者等再生を利用する
債権者の説得が奏功しない場合には、小規模個人再生を諦めるほかありません。
しかし、マイホームなど、手元に残しておきたい資産がある場合には、自己破産を申し立てることを躊躇してしまうケースもあるでしょう。
その場合は、給与所得者等再生の利用をご検討ください。
給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる方のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動幅が小さいと見込まれる方のみが利用できます。
典型的な例として、会社員や公務員など、安定した基本給を受け取っている方は、給与所得者等再生を利用することが可能です。
給与所得者等再生の場合、裁判所は再生計画案について、債権者の意見を聴く必要があるとされていますが、債権者の決議までは必要とされていません。
したがって、仮に再生計画案に反対する債権者が多数であったとしても、裁判所が再生計画を認可すれば、個人再生による債務の減額を実現できるのです。
ただし、給与所得者等再生の場合、小規模個人再生の最低弁済額とは別に、「可処分所得の2年分以上」を弁済しなければならないという条件が適用されます。
この条件により、再生計画に基づいて弁済すべき金額が小規模個人再生と比較して増える可能性がありますので、事前に金額のシミュレーションをしておくことが大切です。
多くの場合、給与所得者等再生の総弁済額は、小規模個人再生よりも多くなることが想定されます。
そのため、原則3年に渡る弁済期間中は、切り詰めた生活をしなければならないことを覚悟する必要があります。
⑷ 自己破産を申し立てる
債権者による再生計画案の決議が見込めない場合には、いっそのこと自己破産をしてしまうのも有力な方法です。
自己破産をすれば、原則として債務全額が免責されるため、個人再生よりも大きな債務の減額効果を得られます。
一方、財産のほとんどを手放さなければならない等のデメリットもありますので、あくまでも個人再生の利用可能性を模索するのか、それとも別の債務整理手続きを行うのかは、ケースバイケースでメリット・デメリットを比較しつつ判断すべきです。
手続きの選択について迷った場合には、ぜひ当法人の弁護士へご相談ください。
4 個人再生に反対する債権者への対応は弁護士に相談を
個人再生手続きにおいて、再生計画案に債権者が反対している状況では、債権者に対する粘り強い説得と調整のプロセスが必要になります。
特に債権者が多数のケースでは、債権者の説得・調整は非常に大変です。
弁護士にご依頼いただければ、反対債権者の説得・調整のプロセスを、弁護士が代理人として対応いたします。
また、他の債務整理手続きとメリット・デメリットを比較しながら、状況に合わせた最適な手続きの選択や、手続きの進め方などについても随時アドバイスいたします。
個人再生をはじめとする債務整理手続きの利用をご検討中の方は、ぜひお早めに当法人へご相談ください。
個人再生手続において再生計画に従った返済が苦しくなったとき お役立ち情報トップへ戻る